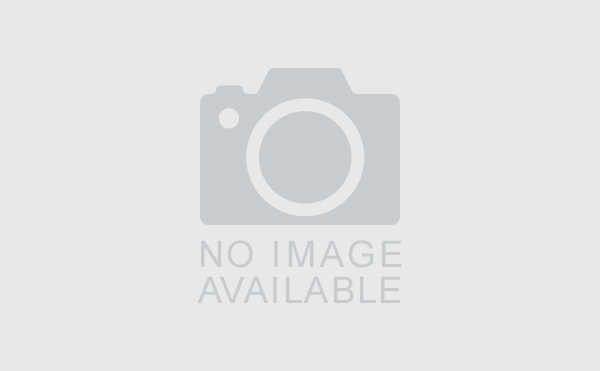佐藤整尚ゼミ
基本情報
概要
データ分析を通してプログラミングを学ぶ。佐藤整尚先生と、学生時代の先輩、そのお二人で顧問をして下さる。先生方が何か教えるというよりは、自分たちでやりたいことをやるゼミ。2024年度Sセメスターは、初学者班と経験者班に分かれて輪読と最終課題(kaggle【データ分析コンペ】など)に取り組んだ。初心者班はデータサイエンスの基本を1から学び、経験者班は画像認識やゲームAIなどについての理解を深めた。
Aセメスターでは班を組み替え、班ごとに活動した。
人数
約20名(3年生20名、4年生16名)
選考の有無
選考あり
活動頻度
毎週月曜日14:55-16:40
卒業論文の有無
必須でない
サブゼミの有無
あり
2年間の合計単位数
12単位
公式SNS・連絡先
X:https://x.com/s_sato_seminar
メール:sato.seisyo.seminar@gmail.com
活動内容
授業計画
3年生と4年生は合同で活動するか
合同で活動予定
ゼミの授業形態(ディスカッションや輪読など)
輪読
来年度使用する予定の教材
初学者は『東京大学のデータサイエンティスト育成講座』を、経験者は指定の教材から一つを班ごとに輪読予定
サブゼミの計画
未定、前年度は「プログラミングのための統計」をメインテーマとし、プログラミングに関連する理論に関して深い理解を目指す。難易度としては、選択必修科目「数理統計」と同程度を想定しており、最終的には統計検定準1級〜1級の取得が狙えるレベルを目指した。
ゼミ合宿
東大山中寮に1泊2日で開催。スポーツなどのアクティビティを始め、BBQ、工場見学などを行うリフレッシュできる合宿となっている。
ゼミの予習
輪読の担当範囲とプロジェクトの進捗状況による。
英語の使用の有無
特に必要ないが、プログラミングを行うのでできて損はない。
他のゼミとの比較
プログラミング初心者でも学びやすい環境が整っている。先生に引っ張ってもらう形式ではないので、そこでゼミの好みが分かれうる。何を学びたいか明確にしておく必要がある。
ゼミ生の属性・進路
女子学生の割合
少数
留学について
留学は可能。毎年1-2名ほど。
兼ゼミ
兼ゼミしている割合
3割
兼ゼミ先
小島、片平、新谷、山口ゼミなど
院進する人の割合
数名
卒業生の就職先
多種多様で、金融からコンサル、ITなど幅広い。SIerやデータサイエンティストなどのIT系専門職が多い。
入会手続きについて
募集対象
東大経済学部の3・4年生(他学部は未定)
おおよその募集人数
約15人
例年のおおよその倍率
約2倍
入会手続きの概要
選考のスケジュール
未定
エントリーシート・面接の有無、形態(テーマ、時間、誰が面接官を担当するかなど)
未定だが、昨年度はES,動画選考,コード問題を課した。
その他
いずれもxやHPで告知予定
ゼミの雰囲気・魅力・大変なこと
ゼミ生の性格やゼミの雰囲気
程よく仲のいい雰囲気で和気藹々と学んでいる。オンオフの切り替えが上手い。
ゼミ以外の時間の交流
月1回ほど飲み会を開催。
各セメスターに任意参加のイベントを実施。
ゼミの魅力
・高いコミットメントを強制されるわけではないが、皆意識を高くもち勉強をしている。
・上級者が教えてくれるので、プログラミング初心者でも学びやすい環境が整っている。
・初心者でも、一年後にはプログラミングが「武器」に変わっている。
・プログラミング経験者は、Sセメスターで余裕そうにしている人が多い。その分Aセメスターで助け舟を出すことが期待される。
ゼミをやっていて大変なこと
・Sセメスター、特にS1に頑張らないと一年間の活動がつまらなく意義を感じなくなる可能性がある。最初が肝心。
・輪読したコードなどは、実際に書いてみないと全く身につかない。
・微積や線形、統計のエッセンスが絡んでくる。経済学部生向けの講義で補完することが望まれる。
・先生に引っ張ってもらう形式ではないので、そこでゼミの好みが分かれるかも。何を学びたいか明確にしておく必要がある。
・基本的に学習内容が経済学部の授業と被ることはないので少なく、機械学習に興味がないと厳しい。